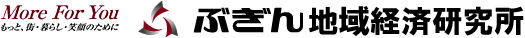ぶぎんレポート
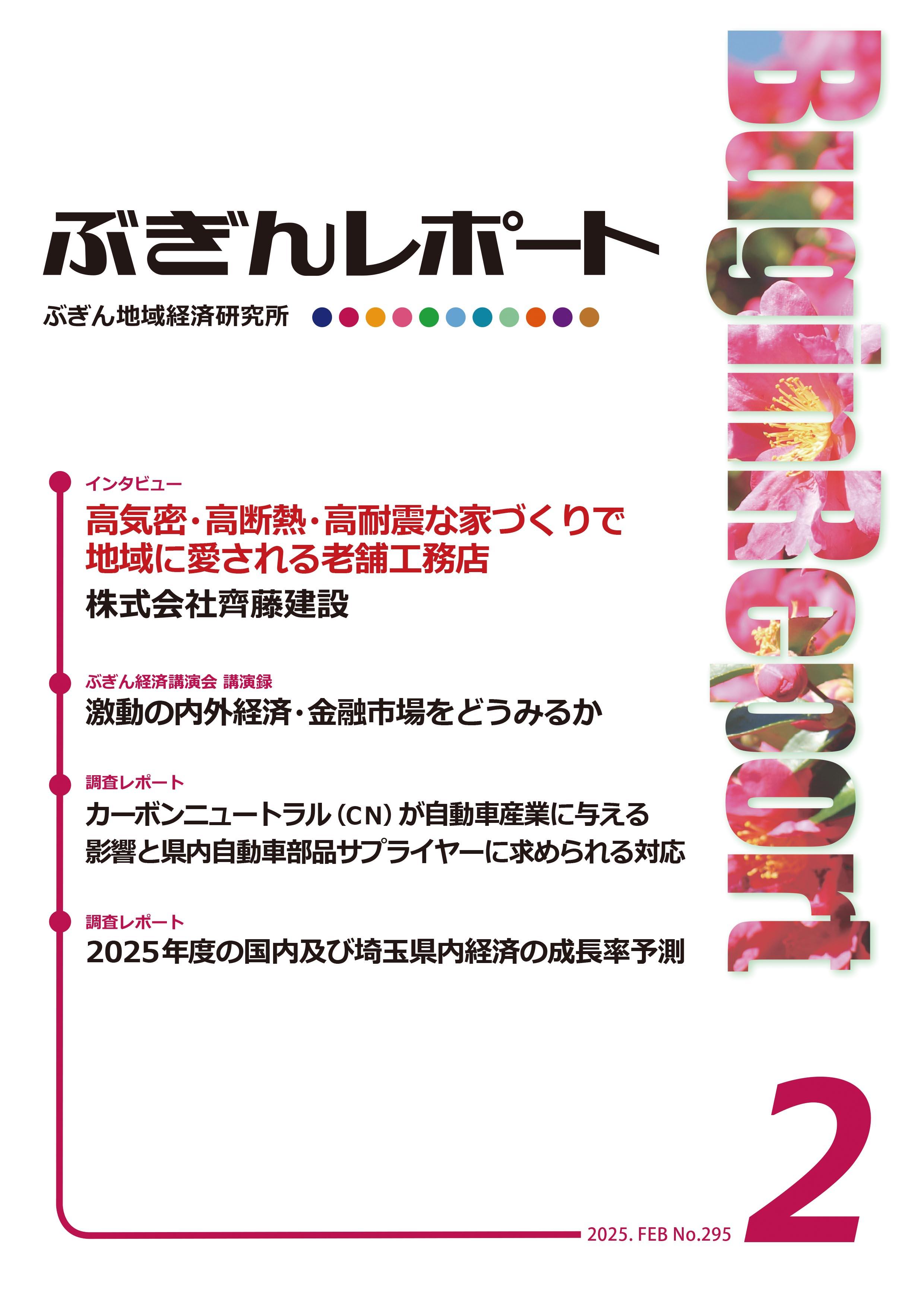
目次
-
企業インタビュー
高気密・高断熱・高耐震な家づくりで 地域に愛される老舗工務店株式会社齊藤建設 代表取締役 齊藤 芳宏 氏
- 鶴ヶ島市で今年創業138年を迎える齊藤建設は、「暮らしを豊かに」という経営理念のもと、太陽光や風など自然の力を上手に活用した、パッシブデザインと呼ばれる環境にやさしい住宅設計を強みとして、一年を通じて空間温度差のない心地良い住まいを実現。自社大工による施工技術にこだわり、現地調査・資金計画から設計、施工、アフターフォローに至る家づくりのすべてをワンストップで提供している。伝統技術の継承と時代に合わせて変革を続ける同社のこれまでの歩みや、家づくりへの想い、課題へのさまざまな取り組みなどについて、4代目である齊藤芳宏社長にお話をうかがった。
-
講演録
ぶぎん経済講演会 講演録激動の内外経済・金融市場を どうみるかみずほ証券 チーフマーケットエコノミスト 上野 泰也 氏
- 2025年には米国でトランプ新政権が始まり、非常に不安定な経済状況が予想されます。一方で、日本では人口減・少子高齢化など、そうした政治イベントに左右されない静かな危機が水面下で進んでおり、それが国内需要を規定する重みを持つということを、改めて意識する必要があります。そういう意味で、日本経済の構造的な弱さと、海外でのイベントに揺さぶられるリスクの両方を見ていく必要があり、以下では、日本経済、日銀の金融政策、米国のトランプ2.0、そして中国経済の順でお話したいと思います。
-
調査レポート
カーボンニュートラル(CN)が 自動車産業に与える影響と 県内自動車部品サプライヤーに求められる対応ぶぎん地域経済研究所 取締役 調査事業部長兼上席研究員 博士(経営学) 藤坂 浩司
- 気候変動に対する産業界の動向が注視されている。わが国では、2020年10月26日、当時の菅義偉総理大臣が所信表明演説で「日本は脱炭素社会の実現を目指す」と発言したことを受けてカーボンニュートラル(以下、CN)への取組みが始まった。翌2021年には具体的戦略が閣議決定され、それを受けて、産業界ではCN達成に向けて、取組みが本格的に始まった。そこで本稿では、自動車部品産業を念頭にCNへの取組みを説明する。CN の達成には、自社の努力、取組みだけでは不可能であり、サプライチェーン全体における二酸化炭素(CO2)の削減が不可欠である。今後、自動車産業では、自動車部品サプライヤーにも協力の依頼が増えてくることが予想される。本稿では前半で概況を説明し、後半ではCNに取組む県内自動車部品サプライヤーの事例を紹介する。
-
寄稿
おかげたまで45周年!テレビ埼玉 感謝と新たな挑戦へテレビ埼玉常務取締役 編成・技術担当 編成局長 大野 茂利 氏
- テレビ埼玉(テレ玉、さいたま市浦和区)は、開局45周年を迎え、さらにパワーアップを図っています。ニュースや情報番組、スポーツ中継の充実に加え、「ゆうひが丘の総理大臣」「キン肉マン」といった懐かしのドラマやアニメの放送、吉本興業とのコラボによるお笑い文化の発信などにも注力。テレビの力を通して地域を元気にするとともに、メディアの多様化に対応し、配信事業など新たな取り組みにも果敢に挑戦しています。
-
地球を守る環境研究の最前線②
災害による断水に備える― 井戸と地域の絆がもたらす力埼玉県環境科学国際センター 土壌・地下水・地盤担当 柿本 貴志 氏
- 埼玉県環境科学国際センターは、「試験研究」「情報発信」「国際貢献」「環境学習」を4つの柱とする環境科学の総合的中核機関です。また、令和4年度からは研究成果の社会実装化を目指した取り組みも進めています。本稿では、断水に見舞われた石川県七尾市民の生活の様子と、市民生活を支えた地域住民の助け合いについて紹介します。
-
これからの経営戦略のキーワードは包摂(第3回)
企業における女性の健幸への取組の捉え方や施策の実態、解決する方向性NTT データ経営研究所 米澤 麻子 氏
- 女性の社会進出が進み、勤労世代の女性の就業率は既に7割を超えています(総務省2023)。人材不足が経営課題となっている昨今、女性が健康で働き続けられる環境を整えることは、企業経営の観点からも重要な課題といえます。女性の健康課題に対する企業の取り組みは単なる福利厚生の一環としてではなく、戦略的な人材活用の観点からますます重要になってくると考えられます。女性が「健幸」でいられる職場づくりは、従業員のエンゲージメントを高め、離職率低下にも効果が期待されます。今後、これらの取り組みを埼玉モデルとして構築し、展開をすることを目指しています。
-
経済コラム
chapter 76「人手が不足していない」企業は、なぜそうなのかぶぎん地域経済研究所 専務取締役/チーフエコノミスト 大西 浩一郎
- 県内企業では、人手不足を訴える声が一段と強くなっています。昨年11月の「ぶぎんレポート」には、筆者による調査レポート「埼玉県の労働市場の現在地」が掲載されていますが、そこでも、「雇用人員BSI」(「過剰」と「不足」の社数構成比の差)は不足超が▲40近傍と過去最悪の水準であることや、主として正社員に関して不足感が強いことを指摘しました。またその背景として、生産年齢人口の減少や正社員の転職市場の拡大を挙げました。もっとも、県内企業の大多数が人手不足なのかといえば、必ずしもそうではない点には注意が必要です。また、転職市場の拡大によって正社員の退職が頻発しているのは事実ですが、一方で、彼らを採用し人員を充足している企業があるはずなのです。このため、「人手が不足していない」企業の声を確かめることは重要であり、人手不足に苦しむ経営者に問題解決の糸口を提供してくれる可能性もあります。
-
埼玉の隠れた銘品百選54
お多福豆きなこまめ株式会社イノウエ
- 秩父郡長瀞町周辺は荒川が削った急峻な河岸段丘にあり、米作には適さないが、代わりに豆が育った。古来より甲州と武州を行き交う人々に提供する中で、豆の加工方法も洗練されていった。「小江戸 まめ屋」のブランドを展開する株式会社イノウエのお多福豆「きなこまめ」は、秩父の風土と磨かれた技法の結晶である。そら豆は、約一週間かける三度の蜜漬けによって濃厚に仕上げる。もう一つの主役、きなこには「秩父借金なし大豆」を使う。この豆は、秩父の村落を貧困から救うために大正年間に生まれた品種で、旨味・甘味が抜群に高いという特長があったが、収穫の手間を理由に作り手が消え、長く幻の豆となっていた。イノウエは、契約農家とともに復興栽培に取り組み、2010年に製品化に成功した。
-
シリーズ 中小企業の経営と営業の戦略
第54回講座弱者の新分野進出戦略のつくり方ランチェスター戦略コンサルタント 福永 雅文 氏
- 大企業と中小企業とでは経営も営業もやり方が違う。小が大に勝つ原理原則と実務として長く中小企業の戦略づくりに活かされてきた「ランチェスター戦略」の専門家で埼玉県の企業の経営相談の実績も豊富なコンサルタント福永雅文氏が中小企業の経営と営業の戦略を事例も交えて解説していく。