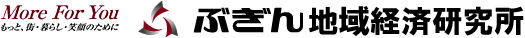ぶぎんレポート
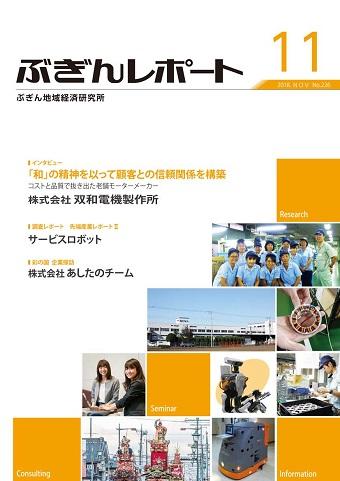
目次
-
インタビュー
「和」の精神を以って顧客との信頼関係を構築コストと品質で抜き出た老舗モーターメーカー株式会社 双和電機製作所 代表取締役社長 長谷川 稔 氏
-
電気エネルギーを機械的エネルギーに変換する装置であるモーター。男子なら子どもの頃に、プラモデルにモーターを組み込んで動かしたことが一度はあるはずだ。電気で動くものにはほとんどモーターが使われており、「モーターの使用量がその国の文化的生活のバロメーターを示す」ともいわれる。
ちなみに日本の家庭内では目に見えないものの、家電製品、給湯器、はたまたスマートフォンを含めて、50個以上のモーターが働いているそうだ。終戦直後に東京・芝浦で産声をあげ、狭山に本社・工場を構える双和電機製作所は、そうしたモーターのなかでも燃焼機器用の小型ファンモーターやポンプ用の小型モーターを主軸としている。500品番以上に及ぶ多品種の製品を小ロットでもスピーディーに納める自社の強みや、今後の展開などについて長谷川稔社長にお話を伺った。
-
調査レポート
先端産業レポートⅡ第2回 サービスロボットぶぎん地域経済研究所 調査事業部 次長兼主任研究員 藤坂 浩司
-
先端産業レポートの第2回は「サービスロボット」を取り上げる。わが国のロボット産業は、生産現場で使われる産業用ロボットを中心に発展してきたが、近年はサービスロボットの市場が広がろうとしている。本稿では、サービスロボット産業の概況と、拡大する市場の背景を示す。次に本県のサービスロボットの動向についてまとめ、今後の産業として発展の課題について述べる。
-
調査レポート
埼玉県内企業の労働生産性向上への取り組みに関する調査
-
〇埼玉県内企業へ労働生産性の向上への取り組みについて聞いたところ、全産業で「すでに取り組んでいる」の割合が47%で最も多く、ほぼ半数を占めている。「今後、取り組む計画がある」とする先は14%で、「計画はないが、今後取り組みたい」とする先は27%となった。人手不足や原材料コスト、賃金上昇圧力が続いている下で、県内企業の9割が労働生産性の向上を経営課題として重視し、前向きに取り組む姿勢にあることが窺われる。一方、「考えていない」とする割合は 12%にとどまっている。
-
彩の国 企業探訪
株式会社あしたのチーム
-
あしたのチームは、AIを利用して企業の人事評価制度をクラウドで提供している。コンサルティングから人事評価制度の構築、運用支援まで幅広いサービスをワンストップで用意している。2018年9月で設立10年を迎え、今後はさらなる発展を目指して人事評価を軸に“人”に関する総合サービスの提供を目指している。
-
経済コラム
chapter 7 中国のタクシーの車窓からぶぎん地域経済研究所 専務取締役 土田 浩
-
中国に出張し、広東省4都市(広州、東ドンガン莞、恵州、深シンセン圳 )と上海を5日間で駆け足で回ってきた。
中国の社会・経済情勢については、仕事柄多くのレポートを読んでおり、専門家の講演を聴く機会も多い。しかしながら、私自身は、中国で現地企業と面談するのは初めてで、観光旅行したのも14年も昔という素人である。今回の中国訪問の目的・成果などは別の機会に譲るとして、ここでは即興で素人の新鮮な印象を綴っておきたい。
-
部下育成にもっと自信がつく12ヵ月
部下の「育てられる力」があってこその部下育成育つ部下と育ちにくい部下の違い株式会社オフィスあん 代表取締役 松下 直子 氏
-
よく育つ部下と、育ちにくい部下の違いは何か。そして、育ちにくい部下がいるとすれば、その部下にどのように接し、どの部分を伸ばしてあげればよいのか。部下の「育てられる力」を最大限に引き出すためのポイントを具体的に解説する。
-
特集 明治維新150周年~武蔵国から埼玉県誕生へ
第5回 埼玉県を“賑わした” 人びとぶぎん地域経済研究所 取締役調査事業部長 松本 博之
-
本シリーズも最終回となりました。これまで幕末から埼玉県誕生までのいきさつをお話ししました。今回は、幕末から明治維新後の時代で、様々な分野で県内とかかわりのあった人物を選んで紹介することにします。
-
JETROアジア経済セミナー
ベトナム社会主義共和国独立行政法人日本貿易振興機構 海外調査部アジア大洋州課 小林 恵介 氏
-
ベトナムの実質GDP成長率はここ10年間、5%台から6%台を維持してきている。また、主要輸出品目は2000年代前半まで、一次産品や軽工業品であり、主要輸入品目は石油製品や生産財であったが、2000年代半ば以降、輸出においては、電気機器や一般機械など、国際分業がなされやすい品目が台頭してきている。2016年に発足したグエン・スアン・フック首相を中心とした指導部のベトナム政府は、2018年の目標について、GDP成長率を6.5%~6.7%としており、マクロ経済の安定を重視した経済運営を目指している。通商政策では、ベトナムは、2001年末の米越通商協定発効や、2007年のWTO加盟などにより、海外市場を新たに獲得し、今後、輸出の更なる拡大、外資企業による対内直接投資の促進が期待される。